研究方法(Research Methodology)とは
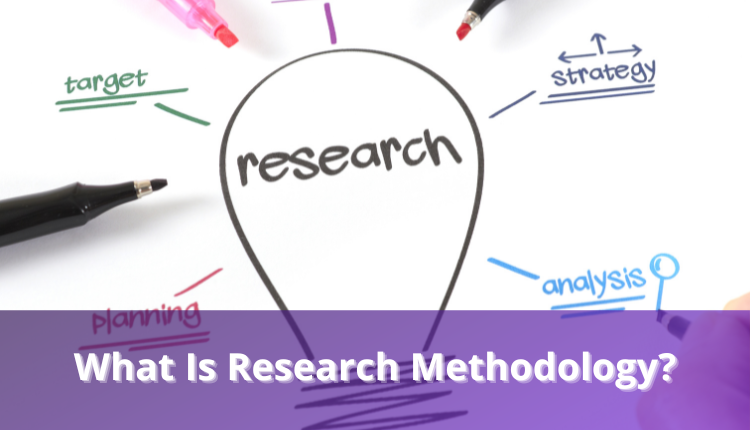
情報を見出す技術ともいえるリサーチ力あるいは調査力は、現代社会では重要な能力です。学生や専門家として学術研究に携わるにせよ、単に必要なものの販売店舗や快適な休暇スポットを見つけるにせよ、ネット上に溢れる情報量のせいで、私たちが日々、リサーチに費やす時間は増えています。
情報の収集とその正しい活用は、習得に時間を要するスキルです。必要な情報を、どう探すか、そして得られた情報が信頼できるものかを確認するにはどうすればいいのか。正確な情報を見出すための方法は様々な領域で確立されています。特に、アカデミックな領域では、それは研究方法論(Research Methodology)と呼ばれます。
研究における方法とは何か、また、何が方法ではないのかを見て、目の前の課題に適した適切な研究方法論を選択する方法を学びましょう。
研究方法論(Research Methodology)とは
Table of Contents
研究方法論とは、研究の指針となる基本的な枠組みの論理です。体系的に使われなければなりません。過度に複雑な方法である必要はありませんが、研究の基盤となるものであるため、選択の背景に、確固たる意図がなければなりません。
学術の世界では、用いた研究方法の説明はどのような論文や研究であれ、不可欠です。
学術系の出版物、特に学術論文の中の「研究方法」のセクション(ジャーナルによっては、「材料と方法(Materials and Methods)」として一つの段落にまとめることを求めるガイドラインもあります。)では、読者は以下のポイントを把握します。
- どのようなデータを収集したか
- どのようにデータを収集したか
- どのようにデータを分析したか
- なぜ、そのような方法を取ったのか
研究方法が重要な理由
例えば、ある病気に対する薬剤Xの効果について、2つの研究があったとします。一方の研究では、Xはその病気にかかっている患者に非常に高い効果を持つとあり、もう一方では、Xはその病気に罹患してから時間の浅い患者にしか効果がないとあります。このような場合、どちらの研究が信頼できるのか、どう判断すればよいでしょう。
実際に、相反する結論を主張する複数の研究が発表されることがあります。通常、そのような異なる結果が生まれた理由は、研究方法のセクションで見つけることができます。たとえば、上の例で、薬剤Xが非常に効果的であるとした研究は、より軽症の患者しか対象としていない可能性もあるでしょう。
あるいは、最初の研究では女性のみを調査し、2番目の研究では男女同数を調査したのかもしれません。2つの研究で投与された薬剤の量が異なっていたのかもしれません。このような情報はすべて、研究方法のセクションに記載されており、研究の本当の意味を理解し、結果の重要度を判断するために不可欠です。
研究方法の種類
研究方法にはさまざまな種類があります。ひとつの方法が他の方法より優れているというわけではなく、方法それぞれに、異なる目的があります。
研究方法は、大きく2つに分けられます。定量的研究(量的調査)と定性的研究(質的調査)です。
一般的に定量的研究の研究方法では、統計やその他のデータ(数値的に捉えられるもの)を、定性的研究の研究方法では、文書の記述や映像、インタビュー、監察結果、歴史的な記録などの質的なデータ(数値的には捉えられないもの)を分析します。
定性・定量融合法研究は、定性的研究と質定量的研究の両方を組み合わせた研究です。
これら3種類の研究方法はいずれも珍しいものではありません。定量的研究の例は、上記の薬剤の有効性に関する研究で、有効性は数値で測定されます(腫瘍が何%縮小したか、白血球数がどれくらい増加したか、患者の意識が回復するまで何日かかったのか等)。
また、ある政策を支持する人がどれくらいいるのか、あるいは原油価格の上昇が一般消費者の食費にどれだけの影響を与えているのかを調べるにも、定量的研究の調査手法が用いられるでしょう。
定性的研究の例としては、人々の認識(選挙討論で誰が勝ったと思うか)、ある概念についての理解(優しさとは何か)、アイデンティティ(性自認や政治的立場)などについてのインタビュー結果を分析する調査などがあげられるでしょう。
定性的研究は、上述のとおり数値化できない現象を理解するための研究方法です。
定性・定量融合法研究は、例えば、ある問題の全体像を把握するために一般人に大規模なアンケート調査を行って質的・量的データを収集しながら、専門家等に対する詳細なインタビュー(キー・インフォーマント・インタビュー)を行い、得られた両方のデータを組み合わせて分析する研究などです。
研究方法の選択と説明
何を目的とし、何を対象とし、何を明らかにしたいのかなどで、研究・調査の方法はある程度決まっていきます。
アメリカ市場でキャンディーを売るための調査であれば、キャンディーの味の嗜好に関し、子どもたちの代表サンプル調査を行い数値的なデータを収集して分析を行うことが有効でしょう。目的が方法を規定するのです。
韓国語の工学用語の多くがドイツ語や日本語由来である理由を明らかにするためには、歴史的な文献のレビューや韓国のエンジニアへのインタビューが役に立つでしょう。質的な研究方法が取られることになります。
学術論文では研究方法のセクションを書く際には、どのような方法を選んだのか、なぜそれを選んだのか、どのように実施したのかを明確に説明する必要があります。
子どもたちを対象に調査を行った場合、どのように被験者となる子どもたちを募り選んだのか、どのような環境でどのような質問をしたのか、なぜその質問をしたのか、得られた回答をどう分析したのか、どのように結果を数値化したのか、などを記述します。
研究論文の読者に、何をどう行い、なぜそれを行ったのかを理解してもらうため、必要な情報をすべて開示します。研究方法、あるいは材料と方法のセクションを読めば、研究を正確に再現できるような記述です。
とはいえ、盛り込むべき要素や記述のルールを覚えてしまえば、研究方法のセクションの執筆はそれほど複雑ではありません。
テクニカルな部分や文法面でのミスを排除するためには、Trinkaなどを活用することで、ライティングの効率を各段にアップできるでしょう。
明確なリサーチクエスチョンと、必要なデータ、分析するための適切な戦略があれば、優れた研究方法を書くための材料はすべて揃っています。
こんな記事もどうぞ
エナゴ学術英語アカデミー – 質的研究の長所と短所
エナゴ学術英語アカデミー – 調査研究に適した統計的仮説検定を選ぶ際の7つの重要項目
エナゴ学術英語アカデミー – インタビューを研究に用いることの重要性とその進め方
エナゴ学術英語アカデミー – 記述的研究の攻略法

